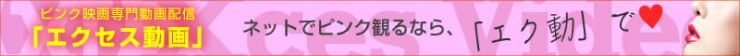浜野佐知監督インタビュー『男社会に喧嘩を売って半世紀!女性監督のピンク映画人生!!』

浜野監督は“戦う映画監督”である。私が浜野監督を始めて知ったのは、1999年前後だったと思う。当時エクセスフィルムは、日活と協力して音の仕上げを一括して日活撮影所で行なおうとしていた。その最初の頃、日活でダビングしていた浜野監督は日活の整音スタッフと大喧嘩したと噂が立った。その理由は分からない。しかし、日活のスタッフに“ピンク映画”、しかも“女性監督”という事で、上から目線の部分があったのではないかと想像してしまう。上からの権威や、女性への差別とは徹底的に戦うのが浜野監督だからである。その後、私もピンク映画を撮ることになり、浜野監督に色々とお世話になるようになった。ある時、旦々舎での浜野組の打ち上げに招かれた事がある。そこでは、浜野監督の手料理にスタッフが舌鼓を売っていた。その時の優しい表情は、まさに“ピンク映画界のお母さん”でもあった。ギネスブック級の本数のピンク映画を撮った浜野監督であるから、助監督として浜野組につき、そこから巣立った監督も多い。ピンク映画界への貢献は多大である。これは、そんな浜野監督への2019年7月5日のインタビューである。
映画監督 工藤雅典
第一回 『少女時代と映画』
【1. 少女が通ったシネマストリート】
工藤:エクセス本社までお越しいただき、ありがとうございます。現在までに撮った映画が、300本を超えると言われている浜野監督ですが、その本数は女性監督としては日本最多ではないでしょうか。まさに日本の女性監督を代表するお一人だと思います。本日は、よろしくお願いします。
浜野:何が「日本の女性監督を代表」するよ(笑)。
工藤:まあ、そうおっしゃらずに(笑)。
浜野:以前、映画評論家の松田政男さんが「数だけだったらギネスブック級」って言ってたけどね(笑)。
工藤:ほんとうですね。早速ですが浜野監督、お生まれは徳島県でしたね。
浜野:そう、徳島県の鳴門市。
工藤:どのような、少女時代をお過ごしになりましたか?
浜野:少女時代ねぇ…。まあ、大人の言うことを聞かない子供だったとは思うけどね(笑)。学校とかの体制に馴染むという事は無かったんじゃないかなあ。
工藤:男の子をいじめたとか?
浜野:そりゃあね。唯一の楽しみだったし(笑)。
工藤:やっぱりですか(笑)。
浜野:少女時代っていくつくらいのこと?
工藤:小学校とか、中学校とかの頃はいかがですか?
浜野:小学3年で静岡に引っ越したんだけど、中学が国立大附属の進学校で、一クラスに男子が30人ちょっとで女子が10人。当然、授業とかも男子中心で回るわけ。それが気に入らなかった(笑)。
それに、医者や弁護士の子供が多くて、クラスのなかにも階級意識みたいなものがあってね。それも気に入らなかった。
私はビンボー人の子どもだったし(笑)。中学に入った年に父親が死んじゃったからね。
工藤:そうなんですか!
浜野:まだ40歳だったんだけどね。脳溢血で、朝、頭が痛いと言って、夕方には死んでた。母と、中1の私、小学3年の弟が残されて、それで、生活がガラッと変わったんだよね。
工藤:それは、大変でしたねえ。

家族写真 左端が少女時代の浜野監督
浜野:父が死んだ時、母はまだ35歳でね、いきなり2人の子供を抱えて、世の中に放り出されたんだから、途方に暮れたと思うよね。当時は結婚したら専業主婦が当たり前だったし、行政に相談すれば「母子寮に行け」、だしね。母子寮になんて行ったら、それこそ差別されるし、あの頃は社会の中に、人種差別、部落差別、当たり前のようにあったんだよね。私の反抗精神みたいなものは、そういう差別に対して生まれてきたように思うね。
工藤:なるほど。
浜野:母は昼も夜も働いて、私たちを育ててくれたんだけど、子供としてはやっぱり寂しかったよね。父親が映画好きでね、毎週土曜日に家族そろって映画を観に行って帰りにラーメン、っていうのが一家団欒だったの。東映のチャンバラとかが多かったけど、父親が死んだ日も映画に行く日でね、私が最後に聞いた言葉が「ごめん、お父ちゃん、頭が痛いんだよ、今日は映画に行けないかも知れない」だった。静岡市の中心街に「シネマストリート」と呼ばれてた通りがあって、映画館が10館くらい並んでいてね。
工藤:ほう。


シネマストリート
浜野:映画に行きたくてね。観たいというよりは、家族団欒を懐かしむような気持だったかもしれないけど、学校から帰ったら、毎日シネマストリートに通ってた。お金がないからポスターや宣材写真を見て回るだけだったけど、それでも何だか落ち着いてね、自分の居場所みたいな感じだった。そしたらある時おじさんに声を掛けられてね、「お嬢ちゃん、映画、好きかい?」って。「うん」って答えたら「じゃあ、観せてあげるからついておいで」って。今だったらヤバイよね(笑)。だけど、ちょうど父親位の齢だったし、ついてっちゃった。そしたら、ミラノ座っていう映画館の一番上の小さな部屋に案内されて、そこが、映写室だったの。
工藤:えっ!そのおじさんは、映写技師?!
浜野:うん。それで、映写室の小窓から映画を観せてくれた。背が届かないからフィルム巻の上に乗ったりして(笑)。
工藤:『ニューシネマ・パラダイス』(1988年公開、イタリア映画、監督 ジュゼッペ・トルナトーレ)みたいな話ですね(笑)。
浜野:ほんとね(笑)。それからは、毎日映写室に通ってね、映写技師のおじさんが、フィルムの事を色々と教えてくれた。「フィルムっていうのはな、生きてるんだ。暑い時は汗をかくし、寒い時は縮こまる。晴れの日も、雨の日もこいつの声を聞いて、一番いい状態に仕上げてお客さんに観てもらうのがおじさんの仕事なんだ」とかね。
工藤:ほう。
浜野:それまで、映画が35ミリのフィルムで、2台の映写機で映写されることも知らなかったけど、おじさんが真剣にフィルムと向き合っているのを見て、映画ってすごいな、って思った。今までは何気なく観てたけど、おじさんのような映写技師がいて初めてお客さんに映画が届くんだ、ということを学んだわけ。
工藤:なるほど。
浜野:高校生になってからは、バイトして好きな映画を観れるようになったけど、そのおじさんの事はずっと忘れられなくてね。いつか私もおじさんのように映画の仕事がしたい、って思うようになった。これが、私の映画監督への道の始まり。
工藤:はい。
浜野:23歳で監督になったけど、ピンク映画でしょ。ミラノ座の隣のビルの屋上に「静岡小劇場」ってピンク映画館があって、そこには舞台挨拶に行ったりしたけど、ミラノ座の敷居は高かった(笑)。
50歳の時から自主制作で一般映画を撮り始めたけど、最初の『第七官界彷徨-尾崎翠を探して』(1999年公開)は静岡東映だったし、やっとミラノ座で上映できたのが自主制作4作目の『百合子ダスビダーニャ』(2011年公開)だった。
工藤:故郷に錦ですね。

ピンク映画館「静岡小劇場」

ミラノ座(2008年)
浜野:ロビーも売店も客席も全く変わってなくてね、感動しちゃった。翌年には解体が決まってたし、ギリギリのタイミングで間に合ってほんと、うれしかった。結局2010年に、シネマストリートの10館の映画館が、耐震の問題とかあったんだろうけど、全部なくなってシネコンになっちゃった。今は、静岡東宝が1館だけ。でも、シネマストリートの名前は残って、通りの両側に、アリフレックスとか、照明機材とか、編集機とか展示してあるけどね。でもミラノ座で舞台挨拶した時、半世紀近くたって、私を映画の道に導いてくれた劇場にやっと恩返しができたような気がしてちょっとうるっとしちゃった(笑)。
工藤:それは良い話ですね。
浜野:映写技師のおじさんは、もういなかったけどね。
工藤:年齢的には、そうでしょうね。でも生きてらしたら喜んだでしょうね。
浜野:でも、おじさんから学んだおかげで、私はフィルムの扱いにうるさい監督だって嫌われちゃって(笑)。
工藤:フィルムの扱いにですか?
【2. 映画館の熱】
浜野:自主制作作品1本目の『第七官界彷徨-尾崎翠を探して』の時だったんだけど、大阪のシネヌーヴォって映画館で上映してくれたのね。私は必ず上映してくれたところには舞台挨拶に行くんだけど、その時は初日にどうしてもスケジュールが合わなくて最終日になっちゃったのよ。
それで上映を観てみたら、なんと、音が出ていない。無音ってわけじゃないんだけど、セリフもよく聞き取れないし、効果音や音楽も高音がすっ飛んだりしてる。もう驚いちゃって、慌てて映写室に飛び込んだら、誰もいない。しばらくしたら若い兄ちゃんがコンビニの袋をブラブラさせて帰ってきて、その兄ちゃんが映写担当だったんだけど、映写技師なんていえないよね。
原因は私の映画の音はモノラルなんだけど、その前に上映した映画がドルビーで、そのまま確認もしないでドルビーのまま上映してた。1週間1日3回よ。27回もこんな音でお客さんが観てたのかと思うともうショックでね。それで、劇場に1回だけでいいから今まで観てくれたお客さんに無料で観せて欲しいって頼んだんだけど聞いてもらえなかった。
知り合いの館主にこのことを話したら、そんなことを要求したらどこも上映してくれなくなりますよ、って言われてね。映画館といえども信用できない、って肝に銘じて、それからはフィルムと一緒に必ず私も付いていって、まずは映写室よ(笑)。
工藤:監督自らですか?
浜野:映写室を見るとその映画館のことがだいたい分かるよね。ただ地方に行くと、もぎりも映写も何もかも一人でやっているところもあるわけで、そういうところでいちいち細かいことを言うと嫌われるよね。だけど、こっちも命がけで作った映画だからね。妥協は出来ないよね。
今までで最高の映写技師だと思ったのは岩波ホールの技師さんだったけど、フィルムが回ってる間はつきっきりで微調整しながら映写してた。映画もどういう映写技師に当たるかで幸せにもなるし不幸にもなるよね。
工藤:最新作(『雪子さんの足音』2019年公開)はデジタルですよね。
浜野:『BODY TROUBLE』(2014年公開)もデジタル撮りだけど、あれはエクセスピンクの『僕のオッパイが発情した理由』のR-15版だからね。でも、それまでは全部35ミリ。私、映画は35ミリだと信じて生きてきたからさ(笑)。
工藤:そうですよね。私もそう思ってました。
浜野:だから、どんな事があろうとも35ミリで撮り続けようと思っていたけど、フィルムが無くなっちゃったんじゃどうしようもないものね。
工藤:それはそうですよね。
浜野:だから、横浜のジャック&ベティとか、デジタルも上映するけど、35ミリも上映できる、という映画館が好き。シネコンが嫌いなの、私は(笑)。
工藤:なるほど。
浜野:映画に対する愛情みたいなモノがさ、その映写技師のおじさんじゃないけれど、映画館にも、有るところと無いところがあってね。『百合子、ダスヴダーニヤ』の時は、ミニシアターとか、運命共同体じゃないけど、映画人としての仲間意識があった。だけど今回の『雪子さんの足音』では、映画館によって全然温度が違う。
工藤:温度ですか?
浜野:うん、映画の作り手が命がけで作ったものを、きちんと観客に届けるという意識のある映画館と、単に映画は商品で、観客に届こうが届くまいが収益があがればいい。ようするに、1日に5本とか、2スクリーンあれば10本とかのスケジュールを組む映画館が多いから、その中の1本をいちいち気にしていられない。だから、「はたしてここの館主は、私の映画を観たのだろうか?」と思うくらい温度差がある。
私はそういうところには、私の映画をかけたくないよね。今はなくなっちゃったけど、下北沢に「シネマアートン」っていう映画館があってね、そこの岩本光弘さんっていう支配人が『こほろぎ嬢』(2006年公開)を上映してくれた時、「たとえ4億円積まれても断る映画もある。今、これは上映すべき映画だ」って言ってくれてうれしかったけど、そういう映画館がだんだん少なくなってきたからね。
工藤:うーん。なるほど。

シネマアートン

『こほろぎ嬢』ポスター
浜野:映画館で上映すると、日報(興行収入)というのが毎日上がって来るんだけど、さっき言ったような、作り手と一緒に観客に映画を届けようという、昔ながらのというか、映画好きというか、そういう映画館というのは、興行収入(の明細)をきちっと出して来るわけよ。でも、そうじゃないところは大体数字がいい加減だからね。
工藤:そうですか。
浜野:今はSNSがあるから、地方の劇場でも、観てくれた人から50人以上はお客が入っていましたよ、とか知らせてくれる。でも、それが日報では20人しか計上されてなかったり。
工藤:ええっ?
浜野:ホントよ! 中には開き直る館主もいるからね。「観に行った人が50人は入ってましたよと言っていたので、20人って間違いじゃないですか?」と言うと「うちだって、そのくらい数字を誤魔化さないとやっていけないんだよ!」とかね(笑)。
工藤:そんなことがあるんですか!
浜野:だから私、必ず契約の時に言うんだけど、観客の人数だけは正直に教えて欲しい、って。ミニシアターは会員制が多いよね。年会費取って、チケット代安くして、スタンプ5つ集めたら1回無料、とかね。本来なら、それだって興収に反映しなければならないはずなのに、優待券とか招待券で観た人は人数に入れてこない。だけど、私にとって大切なのは興収じゃない、観てくれた観客の数なのよ。どれだけの人が私の映画を観たいと思ってくれたか、それが作り手の悦びであり、プライドでしょ?
工藤:なるほど。
浜野:「そんなこと言う配給会社ありませんよ」とか言われるけど、私は監督です!って(笑)。上映も闘いの連続よ(笑)
工藤:うーん。戦いなんですねえ。
浜野:映画撮ってる方が100倍楽(笑)。だけど間に配給会社なんか入れられないものね。だって、映画館での興収が100だとすると、映画館が50、配給会社が50で分けて、制作会社に入ってくるのは配給会社の50の半分。つまり興収の4分の1しか入ってこない。これじゃインディペンデントの映画の制作費なんて永久に回収できないよね。だから、私は自分で配給までやらざるをえない。だけど、ただ、苦労だけじゃなくて、自分の映画を最後まで見届けるというメリットもあるけどね。
工藤:配給も苦労がありますねえ。
浜野:私は、どんなに遠い地方の劇場でも初日には必ず行くようにしてる。アゴアシも自前だし、入場料も自分で払って観る(笑)。それで、色とか音とか、観客の数とかチェックして、ついでに舞台挨拶して帰って来るという(笑)。
工藤:見回りですね(笑)。
浜野:めんどくさい監督だと思われてるだろうけどね(笑)。だけど、そこまでやることが、自分が創った映画への責任だと思うのよ。だって、現場でもポスプロでも全てのキャストやスタッフの技術の積み重ねで完成した映画が、上映で色は出ないわ、音は聞こえないわじゃみんなに対して顔向けできないものね。
工藤:それは、ベストの状態で観て欲しいですよね。
浜野:映画は作品だからね。商品じゃなくて、作品なのよ、映画は。
【3. 社会への目覚めと映画監督への思い】
工藤:当時見て、印象に残った映画はありますか?
浜野:私ね、実は、社会派だったのよ(笑)。
工藤:中学3年からですか?(笑)
浜野:そう(笑)。熊井啓監督(1930~2007)に憧れていてね。
工藤:熊井啓さんですか!
浜野:エクセスの初期は日活撮影所の録音スタジオで仕上げしてたんだけど、ダビングしながらふと後ろを振り返ったら、熊井監督が立って観ててね(笑)、びっくりして思わず「私、監督に憧れて映画監督になった浜野です!」って言っちゃった(笑)。
工藤:ほう。ずいぶんミーハーですね(笑)。
浜野:そりゃそうよ(笑)、だって熊井啓よ、私にとっては映画の神様だったもん。私ね、若いころは民青(日本民主青年同盟)だったんだ。
工藤:そうですか。
浜野:東京に出てくる前の60年代だけどね。原水禁(原水爆禁止日本国民会議)とか沖縄返還とかね、そんな活動をやってたの。
工藤:その活動は、いつ頃までやってたんですか?
浜野:上京するまでかな。民青って18歳になると、必然的に党員になる人が多くてね。
工藤:共産党に?
浜野:そう。私も誘われたんだけど、職業はピンク映画の助監督だって言ったら(入党を)断られちゃった(笑)。
工藤:本当ですか!?
浜野:映画がやりたいなら、党関係の広報とかドキュメンタリーの映画を作ればいいじゃないかって言われたけど、そんなもの作っても面白くも何ともないものね(笑)。ピンク映画が何で悪いんだって啖呵切ってね(笑)、結局民青もやめることになったのね。
工藤:何だか凄いですねえ。
浜野:でも、今でも選挙は共産党以外入れないし(笑)、辺野古に通ったりしてるけどね。
今の沖縄の現状を見てると「沖縄を返せ」(作詞 全司法福岡支部、作曲 荒木栄)と歌った戦いが果たして正しかったのかどうか、沖縄を日本に返せ、じゃなく、沖縄を沖縄に返せ、が正しかったんじゃないかっていう忸怩たる思いがいつも心にあってね、それで、絶対に辺野古に基地を作らせない、という強い思いで通ってるんだけどね。

沖縄タイムスの記事に載った浜野監督
工藤:中学の時からだから1960年代の前半頃ですね。
浜野:ちょうどピンク映画が生まれた頃ね(『肉体の市場』1962年公開、監督 小林悟)。
工藤:監督を志した動機は、先ほど話に出た、映写技師さんとの出会いと言えますか?
浜野:映画の仕事に就きたい、という気持ちはその時芽生えたと思うけど、監督という具体的な目標はなかったんじゃないかな。さっきも言ったけど、シングルマザーの母親を見ていて、世の中には女に対する差別があることを知ったしね。愕然としたけど、社会がこれだけ冷たいなら、生涯、何があっても自分で生きていけるだけの仕事を持とうと思った。だったら、好きな映画を仕事にしたいな、と。ところが大手映画会社の就職条件が「大卒・男子」だったのよ。究極のジェンダー差別だよね(笑)。それで、何とかもぐり込んだのがホモソーシャルな若松プロという…(笑)。
第2回 『女が監督を目指す道』は、若松プロでの葛藤、プロデューサーとしての活躍など、監督デビューまでの波乱万丈の映画修行時代が語られます。乞うご期待!!
*本文中に掲載した写真は浜野監督に提供していただきました。写真協力・「静岡映画館物語」編集委員会