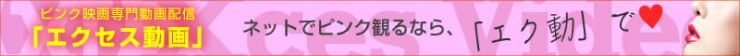ピンクの炎 第2回 「音屋の矜持」シネ・キャビン中村さんに聞く その1「映画少年、雌伏の時代」
[2017年10月3日 新宿「シネ・キャビン」にてインタビュー]
中村幸雄さん(75歳)は、録音スタジオ「シネ・キャビン」の社長として、近年のピンク映画の「音」の仕上げを、ほとんど一手に担ってきました。また、シネ・キャビンは、録音スタジオとしてだけでなく、ピンク映画のスタッフ、キャストが、夜な夜な中村さんを囲んで酒を飲み明かし、夢を語り明かして「梁山泊」とも例えられた集いの場であり、心のよりどころでもありました。自分を「音屋(おとや)」と自称する中村さん。今回は、中村さんに「音屋」として駆け抜けたピンク人生を、存分に語っていただきたいと思います。
映画監督 工藤雅典

工藤:こんにちは、今日はよろしくお願いします。ピンク映画界で中村さんを知らない人はいない訳ですが、今回はもっと広く一般の人にも中村さんを知ってもらいたいと思っています。中村さんはスタッフとして、音の仕上げを幅広くやって来られました。肩書きとしては、「録音技師」と紹介すれば良いですか?
中村:いやあ、「音屋(おとや)」の方がいいんじゃない。俺は、その方がしっくりするよ。録音と言っても、色んな仕事が入るから。
工藤:「音屋」ですか?そうですね、中村さんの仕事は、効果音から整音から、仕上げ作業全部が入る訳ですものね。
中村:うん。一番大事なのは「生音(なまおと)」なんだよね。とにかく、ピンクの場合、同録じゃなかったからね。俺は、生音が好きだったから。
工藤:「生音」とは、サイレント撮影の場合の、台詞のアフレコ以外に、シーン全体につける効果音の録音の事ですよね。僕も、日活のサード助監督の時、効果部のスタッフが、映写を見ながら、靴音や、水の流れ、物を置く音、ドアの開閉音などを、一発録りで、何種類も同時につけていくのを見て吃驚した記憶があります。
中村:いわゆる音の芝居だよね。色々、自分の主張も出せるじゃない。テレビドラマも始まった頃はみんなアフレコだったんだよ。それが、だんだん同録になっていって、ピンクだけが残ったんだよ。だから、ピンクは良いよな、俺の仕事は最後まで無くならない思った。生音は絶対必要だから。
工藤:では、順を追ってお話を聞いていきたいんですが、まず、中村さん、お生まれは?
中村:昭和17年11月12日、鹿児島の甑島(こしきじま)です。
工藤:どういう少年時代でした?
中村:俺は、子どもの頃からこういう事が好きだったからね。小学校の学芸会で効果音をやってたの。
工藤:えっ!小学校の時から!!
中村:そう、声で動物の鳴き声をやったり。それから、自分で幻灯機を作って、友だちを集めて、障子に映して上映したりしてたよ。
工藤:凄いですね。幻灯機の作り方とか、そういう情報はどこで知ったんですか?
中村:鹿児島には、「映画どん」という人がいたんだよ。ほら、「西郷どん」とかみんな最後に「どん」がつくだろ。
工藤:その「映画どん」というのは何をする人なんですか?
中村:何て言うか、巡回映画だよ。「どこどこで、いつやるよ」という貼り紙をして、おっさんの映写技師が1人でやるんだよ。俺は、それについて回って、一緒に貼り紙してあげたり、そういう事をやってたの。それが、小学校の2年くらい、昭和25、6年かな。公民館なんかでやるから、映写機の横でずっと見てたの。そして、フィルムを巻くのを手伝ったり、当時のフィルムはすぐ切れるから大変だったんだけど、本当にそういう子どもだったの。
工藤:その当時見た映画で、記憶に残ってるのはありますか?
中村:時代劇でね、大河内伝次郎の出た「沓掛時二郎(1929年、監督 辻吉郎)」。他にも幾つか、記憶に残ってる映画のシーンがあるけど、そんなに、詳しく知ってた訳じゃない。でも、何かカッコいいのよね。だから、映画をやりたい、映画をやりたいって思ってた。
工藤:そうなんですか。

中村:小学校6年の時に親父が死んで、お袋と二人になって、俺はこれからここで何をするんだろう思った時に、兄弟はみんな東京に出ていたから、俺も東京に出ようと。中学2年の2学期にお袋を説得して、東京の学校に転校したの。
中学卒業して、昭和33年頃だよな、板橋の工場に勤めながら、夜は学校に通って。清瀬に住んでいたんで、そばに大泉があったから、それを見ながら、いつか映画をやりたいと思っていたけど、大泉の門を叩く度胸もなかった。それがある時、昭和36年の夏、池袋の職安に行ったんだよ。もう、腹を決めて、何でも良いから映画の仕事をしたいと。そうしたら、今、大泉で募集してますよと!
工藤:ほう。そんな事があるんですね!
中村:ちょうど、良いタイミングだったんだよね。それで、大泉の東映撮影所に行くと、門番がいたので、職安で募集があるからと聞いて来たと言うと、「ああ、あるよ、照明が良いかい、大道具も足りないと言ってるよ」とか言うの。
工藤:守衛さんですよね(笑)。
中村:守衛?まあ、門番だろ(笑)。それで、本編(映画)の事務所を教えられて、そこへ行くと、「今は、本編はどうにかなってるけど、テレビの方の人手が足りない」と言うんだ。
工藤:東映のテレビプロですね。
中村:そう。テレビプロが出来て何年かしか、たってなかったんだ。そこへ、行ったの。で、試験があるって。
工藤:試験ですか?
中村:そう、試験があるったって、どんな試験だろうと。そしたら、ただ、身体検査だけなんだよね。
工藤:本当ですか。
中村:ただ、体の試験なんだよね。丈夫かどうか。それで、受かったんだよ(笑)。
工藤:とうとう、念願の映画会社、東映に入れて、映画の仕事ができる事になった訳ですね。
その2「怒濤の修業時代」に続く